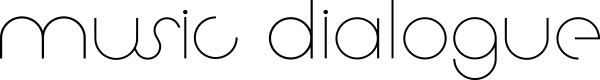Duo Project 特別インタビュー
“ヴァイオリン独奏”でも“ピアノ伴奏”でもない!? ~パリ音の教授と東響のコンマスが語る「二重奏 Duo」の目指すべき道
2021年度に新たに始動する、Music Dialogueの「Duo Project」。秋に開催される「DUOオーディション」に先立ち、7月に演奏会が行われる。本企画にてシュトラウスの二重奏で共演する水谷晃(ヴァイオリン)と上田晴子(ピアノ)に、「二重奏」を学ぶ意義、そして目指すべき道について、それぞれの楽器の視点から、じっくりと話しを伺った。
聞き手・執筆 小室 敬幸(音楽ライター)

ヴァイオリンとピアノ――発表会でも見かけるような、あまりにありふれた組み合わせでありながら、実は多くの問題を抱える編成でもあることをご存知だろうか。ピアノと一緒に演奏しているのに“ヴァイオリン独奏”とチラシやプログラムに表記されたり、ヴァイオリニストとピアニストが出演する演奏会なのに“ヴァイオリン・リサイタル”と題され、ピアニストの写真だけ小さかったり……。なぜ、現状はこのようになりがちかといえば、ピアノは“伴奏 accompaniment(=付属物)”で、ヴァイオリン独奏を引き立てる役割だとみなされているからなのだろう。 しかし、それでは“ソナタ”を演奏する際に、大きな間違いをおかしてしまう。今日、“ヴァイオリン・ソナタ”と呼ばれる作品の大半の正式名称は“ヴァイオリンとピアノのためのソナタ”であり、なかには敢えて“ピアノとヴァイオリンのためのソナタ”と名付けられている作品もある。つまりは両者が対等の関係にあることが、作品理解の最低条件となるはずなのだ。
■ 伴奏者から共演者へ
“ピアノ伴奏”のことを考えるとき、東京交響楽団のコンサートマスターを務める水谷晃は、学生時代に師事していたヴァイオリニスト小林健次先生の言葉を思い出すという。
水谷「大学1年生の時の試験課題がヴァイオリンとピアノのためのソナタだったんですけど、曲を決めている時に“ピアノ伴奏者”と言ったら、健次先生に烈火の如く怒られたんですよ。ヴァイオリンとピアノのためのデュオというのは、むしろピアノの方が主役なんだって言われましたね。」
その後の大学生活4年間のなかで、デュオに対する理解を深めたり経験を積んだり機会は充分にありそうだと思われるかもしれないが、実際はそうではなかった。
水谷「ピアノとヴァイオリンが対等になるデュオを勉強する機会っていうのは学生時代、コンクールや試験を含めても、おそらく1年に1~2曲ぐらいだったと思います。しかも当時は、自分が弾くヴァイオリン・パートをブラッシュアップすることでいっぱいいっぱいになってしまい、デュオとしてどうあるべきかというところまでは考えが至らなかったなと。共演者であるピアニストが(音楽で)何を話しているかを聴く余裕がなかったんでしょうね。」
そのため、往々にしてヴァイオリニストとピアニストがディスカッションしながら音楽づくりをするのではなく、ヴァイオリニストにうまく合わせることに特化した、いわゆる“伴奏ピアニスト”が重宝されることになりがちなのだろう。
現在、パリ国立高等音楽院の室内楽科で教授を務めるピアニストの上田晴子でさえ、若い頃には伴奏者や伴奏ピアニストと呼ばれることが多かったという。

上田「日本で仕事をし始めた頃は、自分が企画したコンサートであってもチラシでは、ヴァイオリニストに比べると小さく名前が書かれ、写真も載せてもらえないなんてこともありました。悲しかったですねえ……。でも、いつの間にか“共演者”として扱っていただける機会が増えて、ここまで頑張って来て良かったなあと思っています。」
ヴァイオリンを習っていた妹と一緒に演奏することに始まり、楽理科出身の母が歌うリートの伴奏をしたり、小学校ではみんなが歌っていた歌謡曲を伴奏したりと、上田は小さい頃からずっと誰かと演奏することを好んでいた。当時はピアノが“伴奏”であることに対して疑念は抱いていなかったが、経験を積み重ねるなかで意識が変わっていく。
上田「私、レッスンの聴講マニアなんですよ(笑)。“この演奏家が好き!”ってなったら、その弟子にくっついってレッスンを受けるんです。高校、大学、留学時代とそういうことをバンバンやっていたお陰で色んなことが学べましたね。初めのうちは誰にでも付いていける、合わせられるのが良い伴奏者で、それがすごいことなんだと思っていたんですけど、段々とそれが嫌になっていったんです。好きじゃない、こういう音楽はやりたくないってものが出来てきたときから、自分は“伴奏者”ではなく“共演者”でありたいと思うようになりました。それで、仕事として伴奏することも辞めてしまったんです。」
水谷「今の(上田)晴子さんの話は、オーケストラにも通じるところがあるなって思いながら聞きました。僕は指揮者がやってることに追随するのがコンサートマスターの役目だと思いながら10年ぐらいやってきたんですけど、最近そうでもないなのかなって考えを改めさせられる経験があったんです。どんなに素晴らしい指揮者であっても、人間ですから得意なところと苦手なところが絶対あるわけで。もしかしたら今まで僕は、その指揮者が苦手としているところも、意図として拾いながらオーケストラをリードしていたのかもしれないなって……。そう思うようになってからコンサートマスターとして、勉強しなくちゃいけないことが増えましたね。基礎がないままアンサンブルなんて出来ないですし、地面にちゃんと足が付いてる状態でないといけないですから。」

誰かひとりに作品解釈や音楽作りを一任してしまうと、何か問題が起きても指摘をしたり、改善をすることが難しくなってしまう。それは音楽に限った話ではなく、日常生活や現代社会、なんなら政治にも通じる話だ。イニシアティブをとる人物にすべてを委任するのではなく、ひとりひとりが能動的に関わることで、より高いところを目指せるようになる(=エンパワーメントを発揮できる)はずなのだ。
■ 実は課題の多いR.シュトラウスのソナタ
上田と水谷、ふたりはピアノ五重奏での共演経験はあるが、デュオとして共演するのは今年の7月13日にHakuju Hallで開催されるコンサートが初めてとなる。演奏されるのは後期ロマン派のドイツの作曲家リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)が若き日に作曲したソナタ 変ホ長調 Op. 18(1887~88年作曲)だ。この曲は上田側からのリクエストであったという。
上田「演奏するのがずっと大変だった作品なんですけど、最近弾く機会が割とあったお陰で、かなり自分の血となり肉となり始めてるんです。だからもう一回弾きたいなと思って。水谷君はオーケストラで長らくコンサートマスターをしているからこそ、R.シュトラウスのオーケストラの音を聞いてる人の演奏はアプローチも違うのかなと思って、結構楽しみにしてるんですよ。」
水谷「この曲ってオーケストラのコンサートマスターが初演した曲じゃないですか?(※当時、ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団のコンサートマスターをしていたロベルト・ヘックマンが初演)。後の管弦楽曲のオーケストレーションが浮かぶような作品でもありますし、どこかで絶対弾かなくちゃいけない曲だなとは思っていました。でも同時に、自分から絶対弾きたくないなってずっと思ってた曲なんですよ。」
上田「え? なんで!?」
水谷「派手だし華やかな作品なので、学生時代に試験などで弾いている人が多かったんですけど、そのどれもが、ずっと同じ感じ、同じ音色で、同じテンションが続くような演奏で、聴いているほうが疲れちゃう経験しかしたことがなかったんです。それで曲に対しても良いイメージを持てなかったんですよ。でも晴子さんもおっしゃった通り、オーケストラプレーヤーが弾くべき曲なのかなって思っていたので、遂にその機会が来たなって感じですね。その1回目が晴子さんとの共演であることが、僕にとって本当にありがたい。感謝しかないです。」
■ なぜ、デュオを学ぶことが重要なのか?
なぜ、水谷の述べたような聴き疲れする演奏が生まれてしまうのか? その要因のひとつには、教育の問題があるのかもしれない。
上田「私が大学院の時にパリからピュイグ=ロジェ先生がいらしたんですけど、“何でみんなコンチェルト(協奏曲)から始めるんだ!?”って強くおっしゃっていたのを覚えています。まずはデュオ(二重奏)で、お互いの音をしっかり聴く。それがちゃんと分かってからトリオ、カルテットと進んで耳を作りなさいとおっしゃっていましたね。」
パリ国立高等音楽院を退官後、1979年に来日してから東京芸術大学で多くの後進を育てた偉大な教師アンリエット・ピュイグ=ロジェ先生の言葉は、非常に重い。更にデュオから学び始める重要性について、上田は自身の経験を加えてこう語る。
上田「デュオから始めることで、いろんな楽器の特性が本当に理解できるようになるんです。弦楽器でいえば例えば弓の特性――今どの位置にあって、どのタイミングでダウン(下げ弓)が来るだろうなとか、そういうのが見てなくても聴こえるようになっていきます。その経験を積むことで、トリオ以上でも何が今起こっていて、自分が何をどうすれば演奏が良くなるのかとか、そういうことも全部分かるようになるんです。でもいきなりトリオ以上から始めてしまうと分かんないんですよね。」
楽器の特性を理解する意義について、水谷は別の角度からも重要性を指摘する。

水谷「(小林)健次先生のレッスンで、“ピアノはヴァイオリンのように弾きなさい。ヴァイオリンはピアノのように弾きなさい”ってことをおっしゃったんですね。相反するといってもいいぐらい構造も性格も異なる楽器が、ひとつの世界を作らなくちゃいけない。そのためにはデュオ通して相手の楽器の特性を理解し、歩み寄る方法を探る必要があります。その方法が分かると、今度はヴァイオリンとクラリネットとか、ヴァイオリンとホルンとか、他の楽器にも全く同じように応用できるわけですよ。」
上田「いろんな音を出すっていう話は、ピアニストは頻繁に求められるんです。フルートみたいな音を出してくれだとか、ホルンみたいな音とかね。でもある時、うちの学校(パリ国立高等音楽院)のマスタークラスに、教授に就任する前のジャン=ジャック・カントロフが来て、その時のレッスンでヴァイオリニストに“他の楽器の音の真似をしろ”って言ってらしたんですね。その時に“わあっ!?”と驚いたことを覚えています。ヴァイオリニストがこんなこと言ってると思って、すごく嬉しかった。」
こうした巨匠たちの金言からも分かるように、“ヴァイオリン独奏にピアノ伴奏が合わせる”という考え方では、良いデュオにはなりえないのだ。そしてデュオで積んだ経験は、もっと編成の大きい室内楽やオーケストラでも活かせるスキルへと繋がっていく。

ヴァイオリンとピアノのデュオが“ヴァイオリン独奏”と“ピアノ伴奏”という関係にならないために、まず何から始めるべきなのか? 最後にふたりはこう語ってくれた。
上田「第一歩はやっぱり楽譜ですね。楽譜っていうのは台本なんです。自分のパート――いわば自分の台詞だけを覚えても、その芝居は全く面白くなりません。話全体がどのように進むのかとか、そういうことを全部理解すると、今度は相手が投げかけてきたものに対して、アドリブでもそうでなくても、返し方が随分と変わってくると思うんですよね。コンテキスト(文脈)を本当に理解していないと、その対応が出来ないし、不自由なままになってしまうんです。それだと伴奏と思われてしまっても仕方ないのかなと。そういう意識で楽譜読んでいくのが、第一歩なのではないでしょうか。」
水谷「相手にたくさん興味を持って、台本を読むっていうことですよね。本当に、これに尽きると思います。そして聴くことは弾くことと同じぐらい大事。良い指揮者はもちろん本当によく聴いてくださるし、良いソリストだって本当によく聴いてくださる。その会話が噛み合った時にそれまで進まなかったものが進むようになるかもしれないし、いろんな展開の可能性をはらんでいるはずなんです。そのぐらい“聴く”っていう行為が本当に大切なことなんですよ。互いを聴きあいながら、色々出しあって、それをまた聴きあいながら、最終的に即興的な要素を交えつつ、その作曲家のスタイルの中で作品が演奏される――。それこそがデュオに限らず、室内楽でもオーケストラでも、全ての音楽における理想的な形だと僕は考えています。」